2025 .12.25
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2011 .08.07
格下げ判断の米S&P、2兆ドルの計算ミスも「影響なし」
(CNN) 米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が米国債の格付けを引き下げた際、米国の財政赤字を実際の規模より2兆ドル(約157兆円)多く計算していたことが分かった。同社はこれを認めたうえで、格下げの判断に実質的な影響はないと説明している。
匿名の政権当局者が語ったところによると、5日午後にS&Pの分析結果を受け取った財務当局者らが誤りに気付き、同社に知らせた。同社はこの時点で誤りを認めたが、格下げの決定は変えず、その日の夜に米国債の格付けを最上位の「AAA(トリプルA)」から「AA+(ダブルAプラス)」へ1段階引き下げると発表した。同当局者は「事実を無視した決定だ。分析は大間違いだった」と主張した。
事情に詳しい関係者によれば、S&Pの格下げについては、「政治的な動き」「判断を急ぎすぎた」と批判する声も上がっている。
S&Pのソブリン格付け部門の責任者、ジョン・チェンバーズ氏は5日夜、CNNとのインタービューで、ミスを指摘されて修正したことを認めた。一方で「米政府の債務残高の国内総生産(GDP)比が今後10年間上がり続けるという事実に変わりはない」と述べた。同氏は、債務上限引き上げをめぐる政治的対立が長引いたことや、引き上げ法の赤字削減策が不十分と判断されたことが、格下げにつながったと説明。さらに、問題の起源は現政権や前政権よりずっと前までさかのぼるとの見方を示した。
(この記事は海外総合(CNN.co.jp)から引用させて頂きました)
(CNN) 米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が米国債の格付けを引き下げた際、米国の財政赤字を実際の規模より2兆ドル(約157兆円)多く計算していたことが分かった。同社はこれを認めたうえで、格下げの判断に実質的な影響はないと説明している。
匿名の政権当局者が語ったところによると、5日午後にS&Pの分析結果を受け取った財務当局者らが誤りに気付き、同社に知らせた。同社はこの時点で誤りを認めたが、格下げの決定は変えず、その日の夜に米国債の格付けを最上位の「AAA(トリプルA)」から「AA+(ダブルAプラス)」へ1段階引き下げると発表した。同当局者は「事実を無視した決定だ。分析は大間違いだった」と主張した。
事情に詳しい関係者によれば、S&Pの格下げについては、「政治的な動き」「判断を急ぎすぎた」と批判する声も上がっている。
S&Pのソブリン格付け部門の責任者、ジョン・チェンバーズ氏は5日夜、CNNとのインタービューで、ミスを指摘されて修正したことを認めた。一方で「米政府の債務残高の国内総生産(GDP)比が今後10年間上がり続けるという事実に変わりはない」と述べた。同氏は、債務上限引き上げをめぐる政治的対立が長引いたことや、引き上げ法の赤字削減策が不十分と判断されたことが、格下げにつながったと説明。さらに、問題の起源は現政権や前政権よりずっと前までさかのぼるとの見方を示した。
(この記事は海外総合(CNN.co.jp)から引用させて頂きました)
PR
2011 .08.06
2/3【経済討論】民主党政権と日本経済の行方[桜H23/7/2]
投資競馬実践書!
注意:決済画面を開くと1000円と表示されますが、万が一、1ヶ月以内に配信
サービスを含め、月に20回以上的中レースが出なければ、購入代金を全額返
金させてもらうことを約束致します。20本以上という数値は利益がプラスになる
コトを計算して出した数値ですので、適当に定めた数値ではありません。
まずは、1000円を預けるという気持ちで本物の投資競馬を楽しんでみて下さい。
もし、貴方が投資ビジネスで億単位のお金を稼ぎたいと本気で
思っているのなら、この手紙はとても重要なモノになります。
今から貴方には投資競馬の全てを体験して頂きますが...
つづき
(この記事はこちらから引用させて頂きました。)
投資競馬実践書!
注意:決済画面を開くと1000円と表示されますが、万が一、1ヶ月以内に配信
サービスを含め、月に20回以上的中レースが出なければ、購入代金を全額返
金させてもらうことを約束致します。20本以上という数値は利益がプラスになる
コトを計算して出した数値ですので、適当に定めた数値ではありません。
まずは、1000円を預けるという気持ちで本物の投資競馬を楽しんでみて下さい。
もし、貴方が投資ビジネスで億単位のお金を稼ぎたいと本気で
思っているのなら、この手紙はとても重要なモノになります。
今から貴方には投資競馬の全てを体験して頂きますが...
つづき
(この記事はこちらから引用させて頂きました。)
2011 .08.05
2011年7月29日(金) 経済産業委員会 泣きの海江田_part_1
東大卒SEの頭脳が開発したFX完全自動売買システム『東大式FX(口座&サポート限定版)』
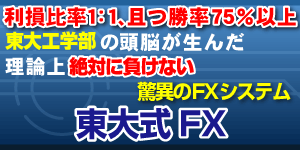
FX自動売買システム「東大式FX」。自動売買ツールの中でも利損比率1:1かつ勝率75%を実現させ、不労所得をあなたにもたらすFX完全自動売買システム(EA)、無料お試し版もご提供中。
詳細
(この記事はこちらから引用させて頂きました。)
東大卒SEの頭脳が開発したFX完全自動売買システム『東大式FX(口座&サポート限定版)』
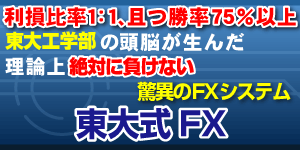
FX自動売買システム「東大式FX」。自動売買ツールの中でも利損比率1:1かつ勝率75%を実現させ、不労所得をあなたにもたらすFX完全自動売買システム(EA)、無料お試し版もご提供中。
詳細
(この記事はこちらから引用させて頂きました。)
2011 .08.05
2011 .08.04
日銀が緩和圧力の強まりに先手、政府協力要請など警戒
[東京 4日 ロイター] 政府による為替介入と連動して日銀が追加緩和に踏み切ったのは、8月予定の基準改定による消費者物価指数(CPI)下方修正に伴う政府サイドからの協力要請や、米経済減速に伴う米金融緩和観測の高まりなどを警戒し、先手を打った側面もあるとみられる。
<欧米債務問題ひと息でも、ジリジリ進む円高を懸念>
日銀は従来から、急激な為替変動は企業経営者らのマインド悪化を通じて景気の下振れ要因になるとして警戒してきた。前回7月の決定会合以降、欧州のギリシャ支援や米国の債務上限問題をめぐり、欧米の金融波乱によるリスク回避資金の流入で急激な円高が進む場合には、追加緩和を辞さない方向で議論を進めていたと思われる。
ただ、欧米発の金融市場ショックが、とりあえず回避されたにもかかわらず、じりじりと進む円高にどう対応するかは、日銀内でも見解の分かれていた可能性がある。為替市場では1日の米市場で一時ドル/円が76.29円と震災直後の史上最高値76.25円をうかがう水準となったものの、日経平均株価は9700円前後のレンジにとどまり、相対的に堅調な動きにもみえた。
<米経済を早くから注視、昨年8月の教訓も背中押す>
その中で追加緩和に踏み切ったのは、米国で債務上限法案が通過後も弱い景気指標を背景に景気減速懸念が急速に高まり、今後米国で追加緩和観測が高まれば、日米金利差などを背景にさらなる円高が更新しかねないとみたからだ。昨年8月も米市場で追加緩和観測が広まり円高が進行。日銀は8月中旬の決定会合では追加緩和を見送り、月末に臨時会合開催に追い込まれたが、こうした苦い経験も今回の追加緩和の背景にあったと推察される。
<CPI基準改定でデフレ議論再燃か>
ただ日銀が非常に懸念しているのが8月に予定されている消費者物価指数の基準改定だ。消費者物価指数はことし4月に2年ぶりにプラス転換したばかりだが、総務省が12日に公表する改定幅は最大0.9ポイント程度との見方もあり、6月実績で前年比プラス0.4%の指数が少なくとも「ゼロ近傍に改定される」(白川方明総裁)のは確実。昨年のたばこ値上げの影響がはく落する10月にはさらに0.3ポイント程度下方修正される見通しで、物価がマイナスとなり、デフレ脱却が遠のいたようにみえる可能性がある。
指数の基準改定で、経済実態が大きく変わることはないが、改定後が真の姿とみられれば、デフレ脱却が遠のくと同時に、通貨の信認が毀損されるようなインフレが発生する危険性は少ないとして、政治・政府サイドから2011年度第3次補正予算などの復興財源をめぐり、さまざまな協力を要請される可能性は否定できない。日銀としては、「常在戦場」の心境で手持ちの政策を総動員し続けることで、政治的なポジションを担保する必要もあったとみられる。
(ロイターニュース 竹本能文 伊藤純夫;編集 内田慎一)
(この記事は経済総合(ロイター)から引用させて頂きました)
[東京 4日 ロイター] 政府による為替介入と連動して日銀が追加緩和に踏み切ったのは、8月予定の基準改定による消費者物価指数(CPI)下方修正に伴う政府サイドからの協力要請や、米経済減速に伴う米金融緩和観測の高まりなどを警戒し、先手を打った側面もあるとみられる。
<欧米債務問題ひと息でも、ジリジリ進む円高を懸念>
日銀は従来から、急激な為替変動は企業経営者らのマインド悪化を通じて景気の下振れ要因になるとして警戒してきた。前回7月の決定会合以降、欧州のギリシャ支援や米国の債務上限問題をめぐり、欧米の金融波乱によるリスク回避資金の流入で急激な円高が進む場合には、追加緩和を辞さない方向で議論を進めていたと思われる。
ただ、欧米発の金融市場ショックが、とりあえず回避されたにもかかわらず、じりじりと進む円高にどう対応するかは、日銀内でも見解の分かれていた可能性がある。為替市場では1日の米市場で一時ドル/円が76.29円と震災直後の史上最高値76.25円をうかがう水準となったものの、日経平均株価は9700円前後のレンジにとどまり、相対的に堅調な動きにもみえた。
<米経済を早くから注視、昨年8月の教訓も背中押す>
その中で追加緩和に踏み切ったのは、米国で債務上限法案が通過後も弱い景気指標を背景に景気減速懸念が急速に高まり、今後米国で追加緩和観測が高まれば、日米金利差などを背景にさらなる円高が更新しかねないとみたからだ。昨年8月も米市場で追加緩和観測が広まり円高が進行。日銀は8月中旬の決定会合では追加緩和を見送り、月末に臨時会合開催に追い込まれたが、こうした苦い経験も今回の追加緩和の背景にあったと推察される。
<CPI基準改定でデフレ議論再燃か>
ただ日銀が非常に懸念しているのが8月に予定されている消費者物価指数の基準改定だ。消費者物価指数はことし4月に2年ぶりにプラス転換したばかりだが、総務省が12日に公表する改定幅は最大0.9ポイント程度との見方もあり、6月実績で前年比プラス0.4%の指数が少なくとも「ゼロ近傍に改定される」(白川方明総裁)のは確実。昨年のたばこ値上げの影響がはく落する10月にはさらに0.3ポイント程度下方修正される見通しで、物価がマイナスとなり、デフレ脱却が遠のいたようにみえる可能性がある。
指数の基準改定で、経済実態が大きく変わることはないが、改定後が真の姿とみられれば、デフレ脱却が遠のくと同時に、通貨の信認が毀損されるようなインフレが発生する危険性は少ないとして、政治・政府サイドから2011年度第3次補正予算などの復興財源をめぐり、さまざまな協力を要請される可能性は否定できない。日銀としては、「常在戦場」の心境で手持ちの政策を総動員し続けることで、政治的なポジションを担保する必要もあったとみられる。
(ロイターニュース 竹本能文 伊藤純夫;編集 内田慎一)
(この記事は経済総合(ロイター)から引用させて頂きました)

